導入事例・コラムCOLUMN
「社員の成長」と「客観的な基準」の両立を目指した昇格アセスメントの設計

20年以上にわたり、管理者適性検査NMAT(エヌマット)を活用している日本光電工業株式会社様。
2023年に新しい人事制度を運用するにあたり、昇進昇格アセスメントを実施する意義や、活用方法の見直しを行っています。
その背景にある考え方、またwebテスティング版NMATの利用に切り替えたご所感について、人事部次長岡村様、小杉様、青山様にお話を伺いました。
INDEX
- 取り組みの背景・課題
-医療機器の先にいる患者さんへの想いが強い社風
-長期ビジョンに基づき役割ベースの人事制度へ改定 - プロセス・実行施策
-新しい目線で昇格アセスメントを見直し
-紙形式からWEB実施に切り替えることで業務生産性が向上
-受検者へのフィードバックへと展開 - 成果・今後の取り組み
-「本来の自分の強みや指向」の自覚を通じて、キャリア開発を強化
取り組みの背景・課題
医療機器の先にいる患者さんへの想いが強い社風

岡村様
岡村様:私は1997年に新卒で入社しました。平塚で11年、浜松と横浜で計8年間営業をし、2015年に人事部に異動しました。人財採用・人財開発チームのマネジャを経て、昨年度から人事部の次長として、人事部全体を見ています。
小杉様:2011年に中途で入社しました。10ヵ月営業本部で数値の取りまとめなどをした後、2年間仙台や福島といった被災地で営業をしていました。人事に異動してから11年目を迎えます。人事としては人事制度の運用や勤怠管理などを経て、人事制度改革を担当していました。2023年の人事制度の改定後は新しく導入した新制度の運用や安定化を担っています。
青山様:私は2021年に新卒で入社しました。人事部人事チームに配属になり、社内の海外トレーニングや駐在員関連業務を担当しています。昇格試験については今年から新しく担当し始めました。また、2年目の時に自ら手挙げをして、さまざまな部署から構成されるグローバル共通価値基準浸透プロジェクトにも携わっています。
小杉様:私が人事として大事にしているポリシーは、社員の目線に立つことです。
具体的には、各種人事制度の納得感や透明性を高めることで、社員から見たときの不条理をなくすことを心がけています。社員が自社の方針・人事制度に納得した状態であることは、本来のパフォーマンスを発揮するうえで非常に重要だと考えているためです。
弊社の社員の特徴は「人に対する想い」が強いことです。
弊社の事業内容は、医用電子機器の開発・製造・販売です。扱っているのは医療機器ですが、社員は皆、その先にいる患者さんのことを考えながら業務にあたっています。そんなビジネスの最前線で誠意を持ちながら働く社員のために、社員のやる気につながる人事の仕組みを整えることが重要です。仕組みや制度は専門的な用語も多く、時に社員にとって分かりにくいこともあるかもしれません。できるだけ社員目線で分かりやすく伝えることで、仕組みの透明性を高めたいと考えています。そういった取り組みにより、社員がより前向きに目の前の仕事に全力を出せることに留意しています。
長期ビジョンに基づき役割ベースの人事制度へ改定

小杉様
弊社では「BEACON 2030」という長期ビジョンを掲げ、2030年3月までを3つのフェーズに設定し、フェーズごとのテーマを着実に達成して変革を成し遂げることを目指しています。「グローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する」ため、今までに培ってきたHMI※技術や医療機器開発の知見に加え、データを中心とした新たなデジタルテクノロジーを活用しながら、これまで以上に人に寄り添った独自のソリューションを創造していきます。
※ HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース):人間と機械との接点。日本光電工業株式会社の場合、センサ技術、信号処理技術、データ解析技術の総称。
Phase Iは基盤の強化(2021年4月~2024年3月)、Phase IIは成長への投資 (2024年4月~2027年3月)、Phase IIIは長期ビジョンの実現(2027年4月~2030年3月)という形で進めていくことになっており、現在はPhase IIにあたります。
人・組織テーマとしては、 「医療への貢献にやりがいと誇りを持てる組織風土の醸成」をマテリアリティに設定し、7つのグローバル共通価値基準を土台として、役割型(職務型)による新人事制度の導入、新たな生活様式に対応した働き方改革の推進、グローバル人財育成プログラムの拡充に取り組んでいます。
新人事制度の導入背景としては、これまでの職能資格制度をベースとしたものから、役割型人事への転換を進めることにより社員の自己実現と会社の持続的成長をつなげていく意図があります。
ちょうど今年から運用をスタートしたのでまだ移行期ですが、人事として今後は新制度が定着するためにさまざまなチャレンジをしていく予定です。
プロセス・実行施策
新しい目線で昇格アセスメントを見直し
人事制度改定にともない、昇格アセスメントも見直すことになりました。
リーダや管理職の役割や期待することについて、社員間で認識がすり合わせができていない状態であると捉え、人事制度の改定に向けて目線を合わせた方がよいと考えました。会社全体で人事制度・昇格制度を運営していくうえでは、リーダや管理職層に対する期待がすり合わされていないと評価や昇格についての納得感が損なわれかねません。客観的なアセスメントを活用することで、役割や期待を明確にしていくことは、人事制度・昇格制度が透明性・納得感を持って運用されるうえで必要であると考えました。
NMATは20年ほど前から昇格アセスメントに使用していますが、選んだ理由の1つが、「客観的なものさし」として機能する、という部分です。
NMATそのものの母集団データが多く、尺度や得点の納得感があることに加えて、弊社内でも20年のデータの蓄積があるので、さまざまな検証分析も可能な状態であり、自社にとってリーダ・管理職に求めるものを確認するうえで有用だと考えました。
今回の取り組みを受けて他社のプロダクトも含め再度昇格アセスメントについて検討しましたが、NMATの信頼感は他社アセスメントと比較して高かったため、人事制度改定のタイミングであらためてNMATを昇格アセスメントの1つに位置づけました。
昇格アセスメントの対象は「メンバ→リーダ」と「リーダ→上級職(マネジメント/エキスパート)」の2つの階層です。「プレゼンテーション審査」に加えて、「NMAT」の結果も確認したうえで、昇格検討を進めています。
データを見て先入観を持つのは好ましくないため、面接官にはNMATの結果は部分的に提示して参考にしてもらっています。また、基準も厳密に設けるのではなく、重視している項目の数値が一定以上あるかを確認する程度の活用にとどめています。
NMATの結果を全面的に信じているわけではないですが、人の目での面接を客観的に補完できる情報があるのは心強いと感じています。
紙形式からWEB実施に切り替えることで業務生産性が向上

青山様
従来NMATは紙での受検だったのですが、2023年からWEB実施に切り替えました。コロナ禍のタイミングで社員全員にPCが行き渡ったことも、WEB実施の後押しになりました。
紙実施の場合は、同じ時間・同じ場所に受検者を集める必要があります。年に1度の日程に照準を合わせて、会場を借りてアナウンスをかけていました。それでも交通機関トラブルなどの想定外の事情もあり、なかなか骨が折れました。
WEB実施は受検者の負担減につながっています。
人事としても上記のような紙実施で発生する多大な工数が削減できたことで、面接オペレーションの改善など、本来時間を割きたい、企画・運営について検討する工数を捻出することにつながっています。
なおNMATの報告書もかつてと比べるとかなり分かりやすくなっており、一人ひとりの特徴が理解しやすいと感じています。人事内でも管理者画面でトライアル受検してみたのですが、自分の結果を客観的に把握できるありがたい情報だと感じました。
受検者へのフィードバックへと展開
NMAT結果は昇格アセスメントに活用していますが、報告書の内容は受検者の今後の活躍にも大いに役立つものと考えています。
「あなたのキャリア開発のために」というフィードバック用報告書は、NMAT受検者の上司や所属部門の責任者にもフィードバックしています。
個人ミッションが中心だった社員が、昇格後にメンバを牽引しながらどのような動きをするかは、なかなか予測がしにくいものです。
そのため、受検者の上司や所属部門の責任者がNMATを見ながら、本人の強みや課題をあらためて理解することには意味があると考えました。本人との面談を通じてNMATの結果を解釈することは、リーダとしての動きをサポートするのに役立つと考えたからです。
残念ながら昇格見送りになった社員についても、上司と本人がNMATの結果を見ながら面談をすることは意義が大きいと思います。単に「ダメだったね」で終わるのではなく、対人面や対課題面における強みや啓発ポイントについて客観的な基準で把握できることで、今後の行動変容につなげてもらう期待があります。
成果・今後の取り組み
「本来の自分の強みや指向」の自覚を通じて、キャリア開発を強化
現在はNMATの結果を本人のキャリアにどう生かすかについては受検者と所属部門に委ねていますが、今後は人事も関わっていくことで、社員自身のキャリア開発によりつなげていきたい、と考えています。
自身のキャリアを考える際に、「現在の仕事」だけでなく「本来の自分の強みや指向」が加わることで、より豊かな道筋が描けるように思います。
人事制度や面談などの機会とNMATを絡めて、有機的な活用を考えていくのが人事としての今後のチャレンジです。
社員一人ひとりがより前向きにキャリアを描き、目の前の仕事に向き合っていけることは、個々のパフォーマンスの向上につながります。そういった社員自身の前向きな状態が、中期経営計画でマテリアリティに掲げる「医療への貢献にやりがいと誇りを持てる組織風土の醸成」につながっていくのではないか、と思います。
NMATの情報をキャリア開発に活用する施策は取り組みが始まった段階ですが、社員・事業双方の成長につなげるべく、今後も模索を続けたいと考えています。
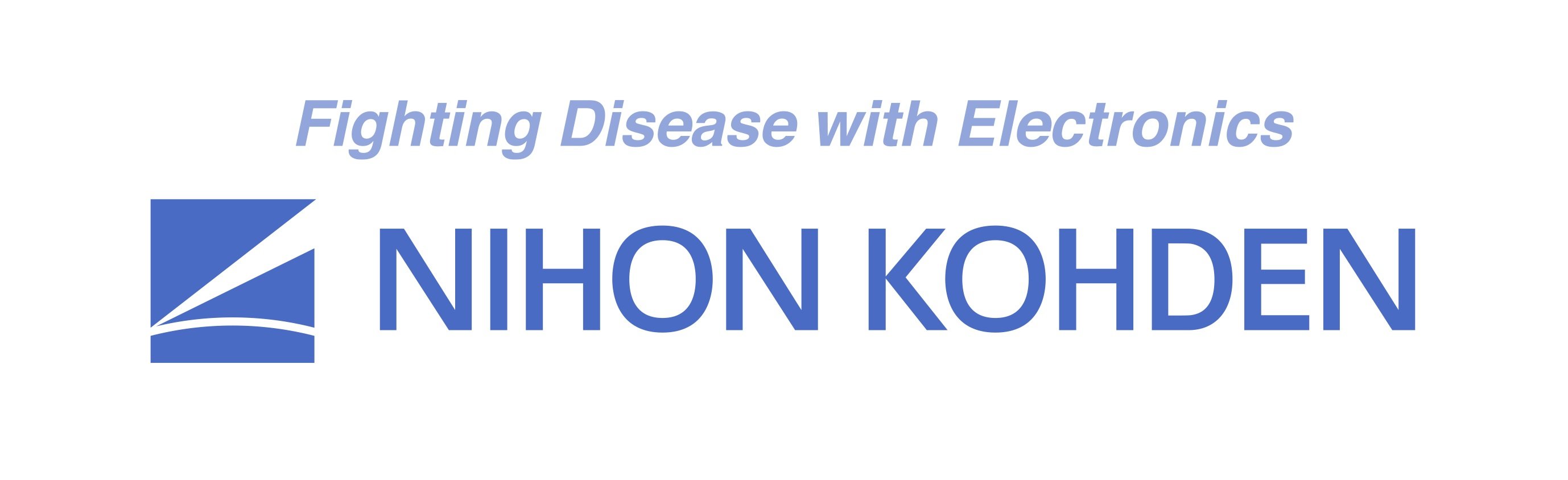
日本光電工業株式会社
https://www.nihonkohden.co.jp/index.html
- 設立
- 1951年8月7日
- 事業内容
- 医用電子機器の開発・製造・販売
- 社員数
- 3,893名(グループ37社6,114名)(2025年3月31日現在)
