導入事例・コラムCOLUMN
長期目線で社員の成長に寄り添うためのアセスメント活用 ~社員一人ひとりの自己理解と学びのために~

株式会社エイト日本技術開発様は、社会インフラ整備を担う総合建設コンサルタントです。
NMAT・JMATを客観的な判断材料としてだけではなく、長期的に事業や社員個人の成長のために自己理解を促すツールとしても活用していただいています。
すでに管理職を担う社員にとっても、結果のフィードバックをきっかけに生まれる新鮮な気づきがあるようです。
その活用内容や、今後に向けた展望をお伺いしました。
INDEX
- 取り組みの背景・課題
-技術職から人事へ。現場のリアルをふまえ、大事にしたいこと
-企業理念実現に向けた求める人材像は「自律的に動ける人材」 - プロセス・実行施策
-導入当初は昇進・昇格基準を補強する客観指標として期待
-導入後は、管理職にとって新たな気づきを促す機会へ
-研修をやりっぱなしにしない。今後に生かす結果フィードバック - 成果・今後の取り組み
-上司とのコミュニケーションツールになることで成長を促進
取り組みの背景・課題
技術職から人事へ。現場のリアルをふまえ、大事にしたいこと

黒木様:私は当初技術職として入社し、区画整理などを担当していました。育児休暇を経たうえで、本社に異動し、さまざまな部署を経験いたしました。人事に来る直前の部署では技術者向けの研修や資格取得支援などを担当していましたが、人事戦略部に異動となり、今では全社共通の研修や新卒採用業務を担当しています。
稲森様:私も技術職として入社しています。道路構造物の設計や橋梁点検の業務、技術本部でISO関連業務などを担当していました。人事戦略部に異動してからは、社員のアップスキリング、リスキリングなど、幅広い人材開発施策を担当しています。
技術力が当社の事業の根幹となりますので、業務遂行にあたって必要な知識を社員に付与する施策には力を入れています。
長く働いている社員であっても、最新の知識に触れることは非常に重要です。また、最近では大学や高専で専門が土木関連とは異なっていたという人でも問題ないように、必要な知識や技術を習得する機会を会社が提供するという取り組みを行っています。
その過程で大切にしていることは、社員の受け止め方や気持ちです。
研修や育成施策に対しては人事としては「良かれ」と思ってやっていることでも、現場からすると「忙しいのに」とか「煩わしい」など、ネガティブな見方もあるかもしれません。
私たちも現場出身者として、そのような現場の受け止め方を想像しながら、その施策を受けることの目的や受講者にとってのメリットなどを人事で整理した状態で施策を展開したり、 重要性を丁寧に伝えたりするようにしています。
そのことを通じて、現場でよりスムーズに、前向きに施策が浸透することを意識しています。
企業理念実現に向けた求める人材像は「自律的に動ける人材」
私どもの企業理念である「価値ある環境を未来に」を実現するために、社員には豊かな社会をつくっていくことに貢献したいという思いや、自然災害などの社会課題にも積極的に関わり、解決しようとするチャレンジ精神を期待しています。
これは人材育成に限らず、採用時に当社が求める人材像でもあります。難しい状況や課題に意欲的に関わろうとする人や、新しいことにも積極的にチャレンジしようとする人を重視していて、採用のホームページにもメッセージを出しています。
また、当社の業務やプロジェクトはさまざまな社内の専門家の知見を生かして、チームで目標を達成する姿勢や力が求められます。同時に、自分なりの意思を持って自律的に動きながら、周囲と協働する力も求められます。
さらに、携わるプロジェクトの地域住民の皆様も私たちの大切な関係者です。最終的なエンドユーザは住民の方々であり、信頼いただきながらプロジェクトを進めていくことが大切です。
実際に私たちが現場で業務を進めていると、プロジェクトについて気にして声をかけていただくような場面もありました。プロジェクト終了まではすべてをご説明できないことも多いですが、丁寧にコミュニケーションを取るなかで安心していただけるようにする、そんな姿勢も求められます。
このように、「価値ある環境を未来に」を実現するうえで、自分の考え・意思を持ちながら、プロジェクトを取り巻くあらゆる関係者と信頼関係を築き、チームで前に進めていくことができる人材を育てていく。それが、私たち人事担当者が取り組むべきテーマだと思っています。
プロセス・実行施策
導入当初は昇進・昇格基準を補強する客観指標として期待

黒木様
NMATは2021年から導入しています。
当時の人事制度において評価の参考となるのは、職能評価や業績評価というプレイヤー時代の情報のみでした。
人事制度改革にあたり、管理職・エキスパート職といった複線型人事制度の導入を検討したことも関係し、「人事で管理職やエキスパート職としての適性も考慮した方がいいのでは?」という課題感を抱いたのがきっかけだったと聞いています。
本人の持ち味を客観的に判定するツールがあれば、上司による人事評価を補完する情報になると思い、アセスメントを導入することになりました。
当初は部長職以上で実施し、結果の確認を行いました。
管理者適性検査NMATを選んだ理由は、世の中の管理職基準との比較ができる点です。
年間4万1千名※1の現役管理職との比較が標準偏差で示されることは、客観的なツールを導入したい、という課題感に合致していましたし、多くの受検者データに基づいて算出されている点が、NMATの信頼性を裏付けるものだと感じました。
業務遂行能力だけでなく、性格特性や役割適性など測定内容が幅広い。さらに納期も短く、費用面も問題ないとのことで導入を決めました。
※1...2025年3月度
導入後は、管理職にとって新たな気づきを促す機会へ

稲森様
当初の導入目的は、役割群を「マネジメント職」に変更する際の客観的な判断指標とすること、そして次期経営層候補者の抽出することでした。それに加えて現在は、結果をフィードバックし自己理解を深めるためのツールとしても利用しています。
具体的には、管理職になって数年が経過したあと、世の中では次長クラスに該当する等級の社員を対象にNMATを受検してもらっています。WEB受検(※管理者適性検査NMATのみ)なので、忙しい現場でも無理なく受検が進んでいます。
そして、受検後は中級管理職研修のコンテンツの1つとして、NMATの結果を本人にフィードバックしています。
この層は新任管理職時の研修で、マネジメントの基礎知識は身につけていて、そこから数年、マネジメントの実践も積んでいます。
だからこそ、自身の経験に加えて、本来的な特性情報を理解することで、さらにマネジメントに磨きをかけてほしい、という目的がありました。
研修をやりっぱなしにしない。今後に生かす結果フィードバック
研修受講後のアンケートで、印象深いコメントをもらっています。
「マネジメントという立場上、自分とは違う顔で、ある意味役割を演じている部分があったが NMATの結果は自分の性格や特徴を非常によく捉えているなと感じました。あらためて職務タイプが自分の思考と特性にあてはまっていて、自分らしく取り組めばよいところと、今後取り組むべき方向性が見えた感覚を持ちました」というもので、まさに人事としても目的にかなう感想をもらえたと思っています。
私(黒木様)自身、NMATを受けた時に指向や特徴が合っている、と感じました。特に、経験則に基づいた判断に頼りがちということで、これは確かにそのとおりだと思いました。NMATで自分の特性や強みと同時に、弱みを知ることができるのは学びになります。弱みの部分は、自分は苦手だから(避ける)、ということではなくて、それならどう変えていこうという方向に考えを切り替えるきっかけになればいいですね。
管理職に限らずですが、ある程度一定の職務でキャリアを積んだ方は経験があるので、自分の本来的な強み・弱みは分かりづらいことがあります。
年齢や職階があがれば、自分の持ち味をあらためて考える機会、ましてや客観的な情報としてフィードバックをもらう機会はめったにありません。普段仕事をしていて自分のことを振り返る機会はなかなかないので、仕事の時に生かせるしっかりとした結果を得られるのは良いなと思っています。
人事としても、研修のやりっぱなしを防ぐのはもちろんのこと、知識付与以外に「本人の役に立つ」「今後に生かしてもらう」ことにつながる施策だと感じています。
その点、NMATには本人が受け入れやすい・理解しやすい、本人に返却する専用の報告書(「キャリア開発報告書」)があることも助かっています。
さらに研修参加者ごとで相互理解のためのグループワークも実施しています。
このグループワークは管理職同士の交流の場になるだけではなく、お互いの理解や悩みの共有などが進む、とても重要な場になっています。
成果・今後の取り組み
上司とのコミュニケーションツールになることで成長を促進

弊社の場合、もとより社員は技術者気質が強いため、データや客観的な情報を分析に活用することに積極的な社員が多い気がしています。
弊社はNMATに加えて、中堅社員適性検査JMATも活用しているので、本人特性を客観的に捉え、今後の業務やキャリア開発に生かしてもらう動きは、管理職層以外にも広がっています。具体的にはNMATの中堅社員層バージョンのJMATという検査は、入社10~15年で、後輩がある程度増えてきた年代の社員に受検してもらっています。
JMAT受検者はまだ管理職経験がない層なので、今後の自身のキャリアを若い年齢から幅広く考えてもらうことを目的に実施しています。
そのようなデータに馴染みやすい風土も背景にあるため、今後は上司なども巻き込んだ、立体的な取り組みへと展開していきたいです。
職場への影響が大きい管理職は重要な存在ですし、将来企業を引っ張っていく人材を育てていくことも併せて求められます。
NMATの情報と、上司の目を併せて活用しながら会社全体で社員の育成を考えることができれば、本人にとってもさらに新たな気付きやキャリアの道が見えるかもしれません。人事としても支援していきたいと考えています。
人事の私たち自身、一受検者としてNMATの結果を見て、自分の得手・不得手を勘違いしていたと気づいた経験がありました。
その時に、「本来の強みを生かしてもっとチャレンジをしないと」と前向きな気持ちが芽生えたと同時に「人は、何歳になっても変わることができる」と、人の成長への考え方がセットされました。
特に長く勤めている社員が多い弊社では、人事としては「人は何歳になっても成長できる」という考え方をベースに、中長期で社員と伴走できるような施策を模索していきたいと思っています。
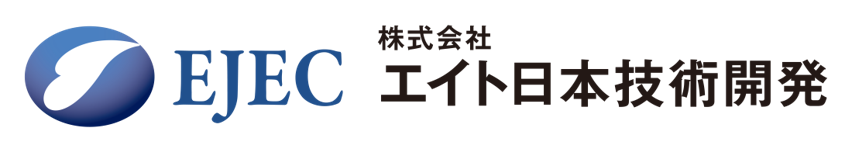
株式会社エイト日本技術開発
https://www.ejec.ej-hds.co.jp/
- 設立
- 1955年(昭和30年)3月1日(創業)
- 社員数
- 社員数 1131名(技術系 935名/事務系 196名)
※2025年6月1日時点 役員含む
